「良いシナリオ」や「悪いシナリオ」という誤解
シナリオプランニングでは、設定したテーマや自社の状況を念頭におき、それらに影響を与える不確実な要因を元にして複数の世界を検討します。
検討した複数の世界のことを「シナリオ」と呼び、そのような複数のシナリオを元として、顧客ニーズの変化や自社の対応を検討することを「シナリオプランニング」と呼んでいます。
ただし、この「シナリオ」という言葉は、シナリオプランニング以外の場面でもよく使われています。
そのひとつが、未来のある状態を想定し、想定よりも良くなった状態を「ベストシナリオ」、悪くなった状態を「ワーストシナリオ」として考えるような場面です。
たしかに、この考え方はシナリオプランニングとよく似ていますが、シナリオプランニングとこの考え方の大きな違いは、何を前提として複数のシナリオを考えているのかという点です。
「ベスト/ワーストシナリオ」という形式で考える場合、通常は、ひとつの想定を前提とし、その振れ幅(ぶれ)の範囲の上限と下限をシナリオとして表現します。
一方、シナリオプランニングで考えるシナリオは、通常は、4つをまったく別の前提で描きます。そのため、まったく違う、それぞれが独立した複数の世界(シナリオ)がつくられます。
そうではあるのですが、複数のシナリオを並べてみると、どうしても「これが良いシナリオ」「これは悪いシナリオ」というように、わかりやすい価値判断をしたくなってしまいます。
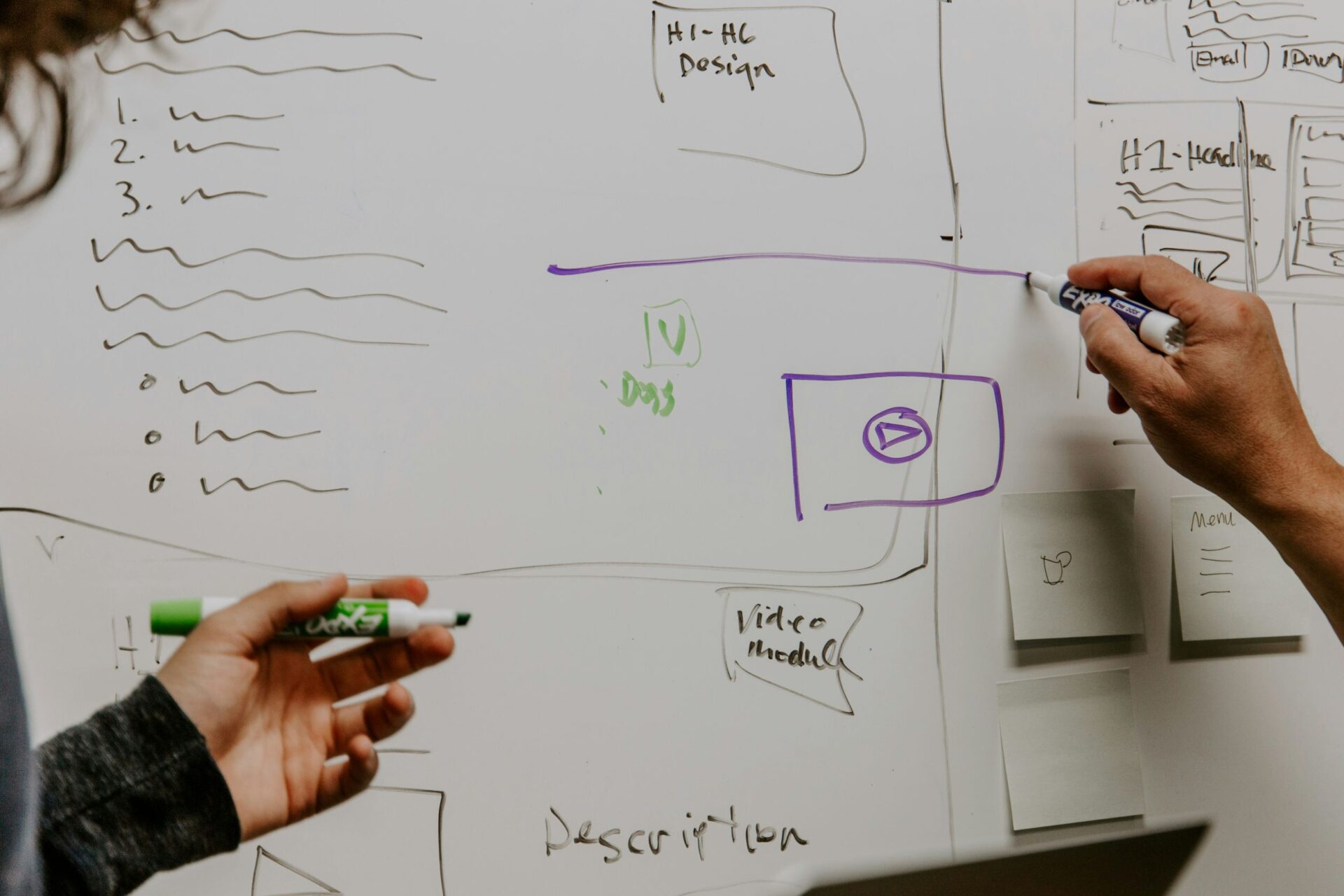
しかし、シナリオプランニングでは、通常、個々のシナリオに「良い」「悪い」といった画一的なラベルをつけることはありません。
たしかに自社にとって都合の良いシナリオというのはあり得るかもしれませんが、そのシナリオになったとしても、すべてにおいて「良い」ということはないでしょう。
現在のように、明らかに悲観的にしか見られない状況の中でも、見る視点や見る時間軸などを変えてみると、そこに機会があるかもしれません。
一見「良い」ように見えるシナリオの中にリスクを見出し、そのための備えをする。
一見「悪い」ように見えるシナリオの中に機会を見出し、その活かし方を考える。
このようなプロセスをとおして、自社や自分が明確に意識せずに抱いている環境や自社を見る「思い込み」に気づくことが、シナリオプランニングに取り組む価値なのです。
そのような価値を十分に享受するためにも、シナリオをつくる際についつい抱いてしまう「良い/悪い」という見方を捨て、世の中はもっと多様で複雑であるという前提でシナリオプランニングに取り組みましょう。
コラム執筆者:新井 宏征(あらい ひろゆき)

株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役
東京外国語大学大学院修後、SAPジャパン、情報通信総合研究所(NTTグループ)を経て、現在はシナリオプランニングやプロダクトマネジメントの考え方を応用し、事業と組織の両面からクライアントの変革を支援するコンサルティング活動に従事。
Saïd Business School Oxford Scenarios Programmeにおいて、世界におけるシナリオプランニング指導の第一人者であるRafael Ramirezや、Shell Internationalでシナリオプランニングを推進してきたKees van der HeijdenやCho-Oon Khongらにシナリオプランニングの指導を受ける。
その内容を理論的な基礎としながら、2013年の創業以来、日本の組織文化や慣習にあわせた実践的なシナリオプランニング活用支援を行っている。
資格として、PMP(Project Management Professional)、英検1級、TOEIC 990点、SAP関連資格などを保有している。
主な著書に『実践 シナリオ・プランニング』、訳書に『プロダクトマネジャーの教科書』、『成功するイノベーションは何が違うのか?』、『90日変革モデル』、『世界のエグゼクティブが学ぶ 誰もがリーダーになれる特別授業』(すべて翔泳社)などがある。
