シナリオプランニングの作り方と使い方
新刊『実践 シナリオ・プランニング』ではシナリオプランニングの「作り方」と「使い方」について詳しく解説しています。
全7章をとおして、シナリオプランニングの必要性やそれを踏まえた作り方と使い方についてご紹介していますが、作り方・使い方を直接紹介しているのが、次の3つの章です。
第4章 実践(1):未来創造ダイアローグ(シナリオを読み、対話する)
第5章 実践(2):未来創造ダイアローグ+(用意された軸を組み合わせてシナリオをつくり、対話する)
第6章 実践(3):シナリオ・プランニング(ゼロからシナリオ・プランニングを実践する)
この中でも「作り方」について解説しているのが第6章です。
ここでは、ウェブでも紹介しているシナリオプランニングの7つの作成ステップを詳しく解説しています。
この第6章だけで200ページ近くあり、これだけで一冊分という感じの内容です。
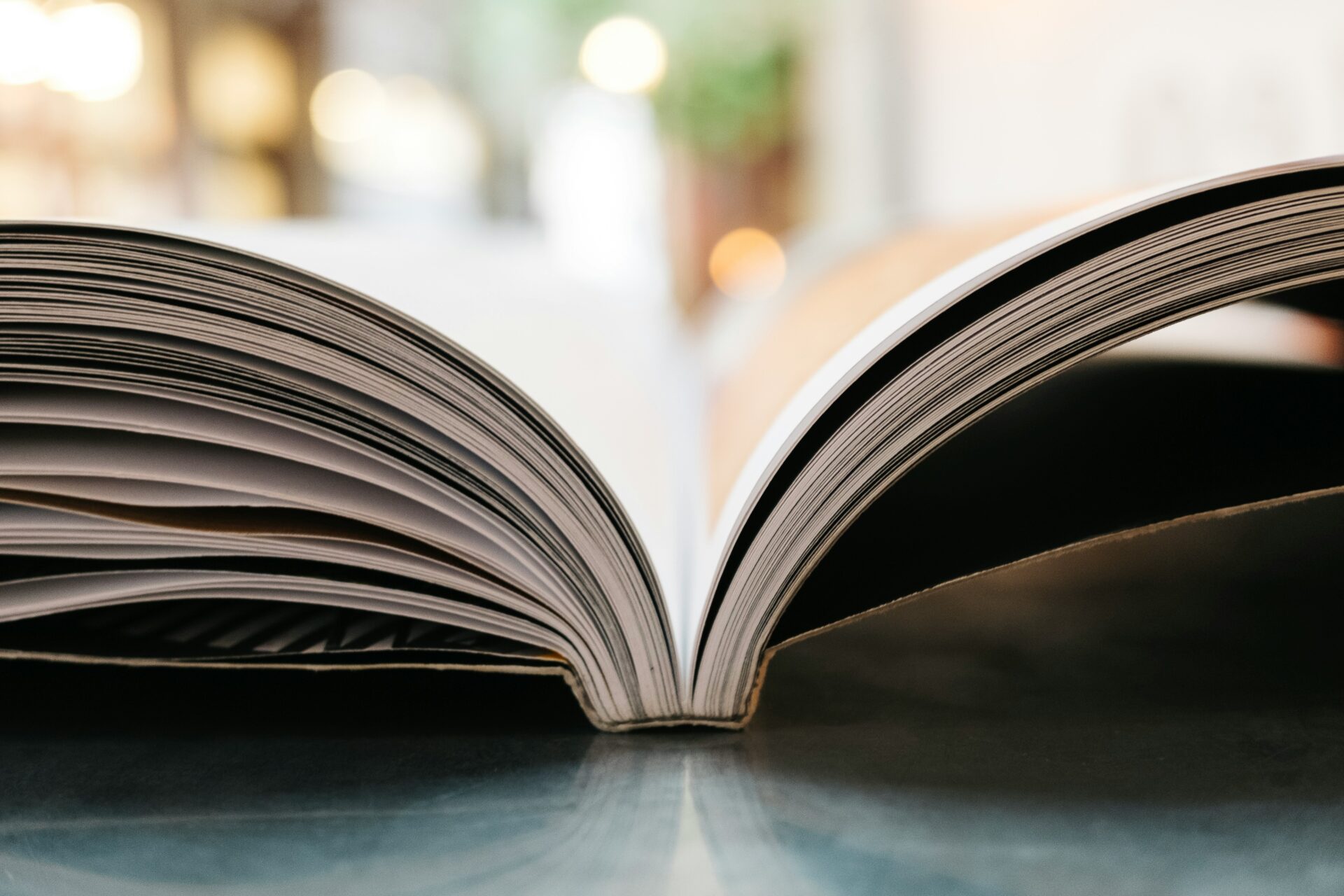
これまでのシナリオプランニングの本というと、この「作り方」のところに重点を置いているものがほとんどでした。
ただし、実際に企業などでシナリオプランニングに取り組むと、シナリオをつくる部分にだけ目を向けているのは不十分であることがわかります。
通常のシナリオプランニングプロジェクトでは、シナリオ作成にかかわるのは組織全体の一部のメンバーだけです。
しかし、現在のような不確実な時代には、組織の一部の人だけが、これから起こり得る不確実な可能性を理解していて、トップダウンで対応策を検討し、実行を指示する…というような動き方では十分ではありません。
組織のすべてのメンバーがシナリオで描かれた不確実な可能性を理解し、それを踏まえて、ひとりひとりが自分なりに起こり得る可能性への向き合い方を考えなくてはいけません。
そのためには、作成したシナリオを組織内で活用する「使い方」にも目を向ける必要があります。
その内容を整理したのが、上に載せた章立ての第4章と第5章で紹介しているシナリオプランニングを元にした対話手法「未来創造ダイアローグ」です。
「作成したシナリオを組織で浸透させることが必要ですよ」ということは、これまでもお伝えできていましたが、じゃあ、具体的にどのように浸透させれば良いのかには、なかなか答えられていませんでした。
そのための方法を確立すべく試行錯誤した結果、体系化したのが、第4章と第5章で紹介している「未来創造ダイアローグ」です。
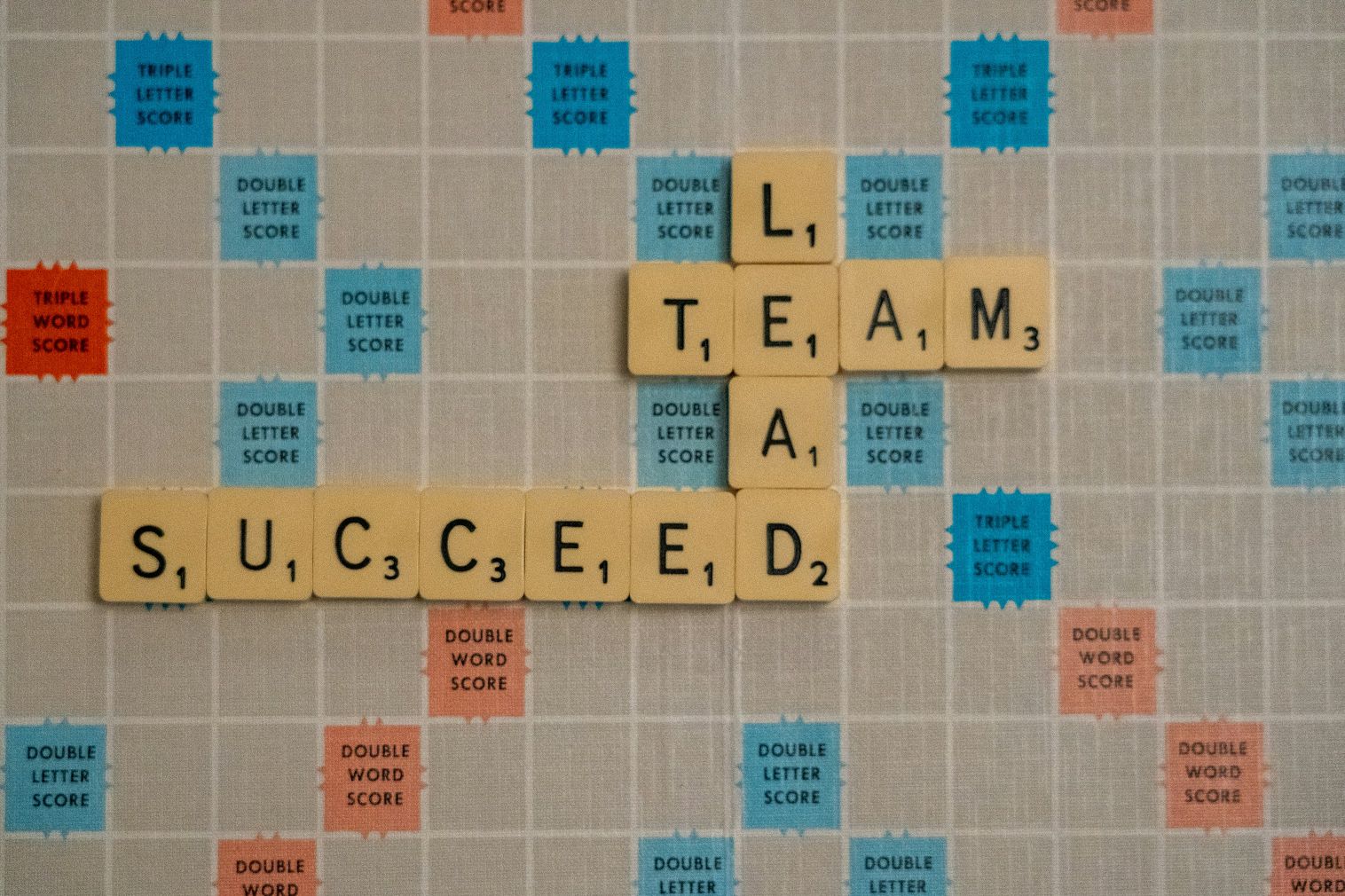
シナリオプランニングは、将来における不確実な可能性への対応方法を検討し、その対応を考える手法です。
そのため「作り方」を押さえるだけではなく、「使い方」にも目を向け、プロジェクトの設計や組織での取り組みを進めることが大切です。
つくって終わりにしないシナリオプランニングの取り組みを、ぜひ心がけてください。
コラム執筆者:新井 宏征(あらい ひろゆき)

株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役
東京外国語大学大学院修後、SAPジャパン、情報通信総合研究所(NTTグループ)を経て、現在はシナリオプランニングやプロダクトマネジメントの考え方を応用し、事業と組織の両面からクライアントの変革を支援するコンサルティング活動に従事。
Saïd Business School Oxford Scenarios Programmeにおいて、世界におけるシナリオプランニング指導の第一人者であるRafael Ramirezや、Shell Internationalでシナリオプランニングを推進してきたKees van der HeijdenやCho-Oon Khongらにシナリオプランニングの指導を受ける。
その内容を理論的な基礎としながら、2013年の創業以来、日本の組織文化や慣習にあわせた実践的なシナリオプランニング活用支援を行っている。
資格として、PMP(Project Management Professional)、英検1級、TOEIC 990点、SAP関連資格などを保有している。
主な著書に『実践 シナリオ・プランニング』、訳書に『プロダクトマネジャーの教科書』、『成功するイノベーションは何が違うのか?』、『90日変革モデル』、『世界のエグゼクティブが学ぶ 誰もがリーダーになれる特別授業』(すべて翔泳社)などがある。
