シナリオプランニングの学び方
なぜ英語学習本が出続けるのか?
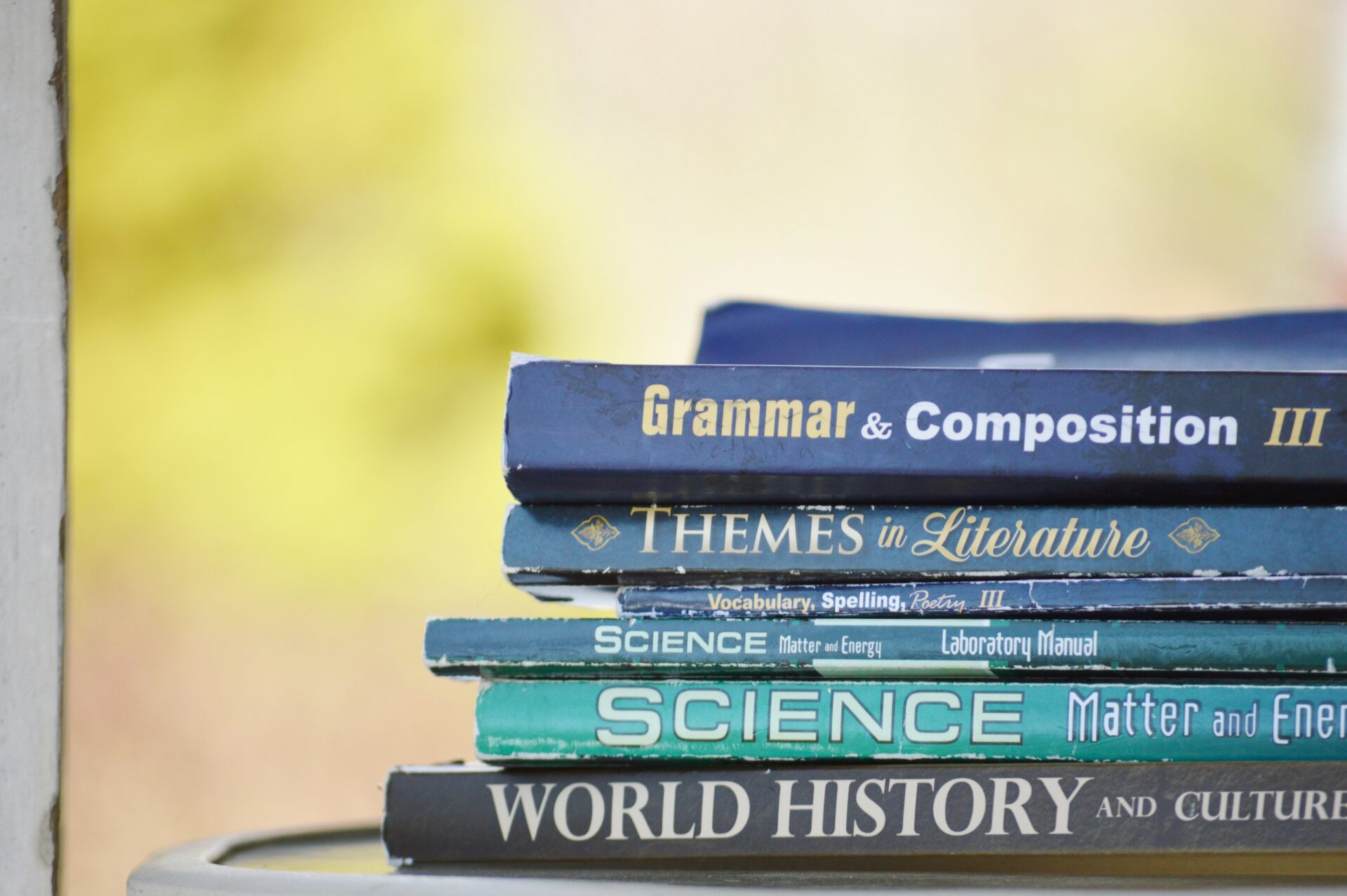
忙しさにかまけてサボることが多いのですが、いまだに日々英語の学習を続けています。「さびつかないようにするために学習を続けている」と言えればかっこいいのですが、英語でのファシリテーションをご迷惑ないようにこなすためには、まだまだ研鑽が必要です。
そういった状況なので、英語学習関連の新刊はよく確認しているのですが、興味深いのは、いまだに「英語学習法」に関する新刊が途切れず出てくることです。
これだけ多くの人が英語を学習しているのですから、さすがに「学習法」を指南するようなものは十分浸透しているのではと勘違いしそうになりますが、そうではないようです。
もちろん、過去に出たものとまったく同じような内容の本であればニーズもないでしょうが、そうでもないようです。私が学生の頃は、いわゆる英語の達人と呼ばれるような人の個人的な体験を交えたものが多かったように思います。しかし、最近は第二言語習得論や認知言語学などの知見を元にした「科学的」なものが増えています。また、生成AIを活用することを薦めるものも増えてきました。
しかし、いくら理論やAIが進化したとしても、学習のために使われるのは私たちの脳ですから、本質的なところが大きく変わるわけではないでしょう。それでも、「英語学習法」本の需要があるのは、私たちが学んでいる過程でなかなか伸びを感じられない際にふとよぎる「この学習法がイマイチなのではないか…?」という、あの感覚があるからでしょう。
正直なところ、私自身も、そう感じて別の参考書に手を出したことはしょっちゅうあります。しかし、同じ内容について他の意見に触れることが参考になることはあるものの、結局、何かを習得するためには、その分野の体系を理解し、自然とできるようになるまでくり返すことしかないと痛感します。
短期間でシナリオプランニングをマスターした人の共通点

いきなりシナリオプランニングとまったく関係のない話しをしましたが、これはシナリオプランニングを学ぶ際にも通用する話しだと感じます。
実はここ数ヶ月で、数回の研修、あるいはワークショップの中で、ほぼ完璧といって良いほどのシナリオ(ベースシナリオと複数シナリオ)をつくり上げた参加者の方がいます。
現在、プライベートレッスンを受けてくださっている方も、同じ状況で、基本的なことをお伝えする必要がまったくないので、数回しかやっていないにもかかわらず、かなり本格的な内容にまで踏み込んでシナリオ作成を進めています。
振り返ってみると、毎年、数名はそういう方がいらっしゃいます。
思い返してみると、そういう方に共通しているのは拙著『実践 シナリオ・プランニング』を本当に丁寧に、文字どおり「隅から隅まで」読んでくださっていて、著者である自分よりもどこに何が書かれているかをご存じなのではないかと思うほどに読み込んでくださっています。
あの本は、私自身が学習者としてシナリオプランニングを学んでいた時に「ここはどう判断するんだ?」とか「独りよがりではなく周りに受け容れてもらうシナリオにするにはどうすればいいんだ?」とか悩んでいた点を、自分なりに検証していった結果を言語化したものです。
言い換えれば、シナリオプランニング実践のステップを知るだけではなく、各ステップに取り組む際に判断しなければいけない点も含め、自分ひとりでシナリオ作成ができることを狙って書いたものです。
たしかに、私の本では私なりの判断基準などを盛り込んでいますが、それは元々あったシナリオプランニングの体系に沿った補足的なものであり、メインでお伝えしているのは長年の実践を経て整理されてきたシナリオプランニングの体系です。
ですので、あの本に書かれているシナリオプランニングの体系を理解し、それを忠実に再現できるところまでくり返していただいた方は、たった数回の研修やワークショップであっても、驚くほどの質のシナリオをつくっていただけたのだと思います。
目的に立ち返って、腰を据える
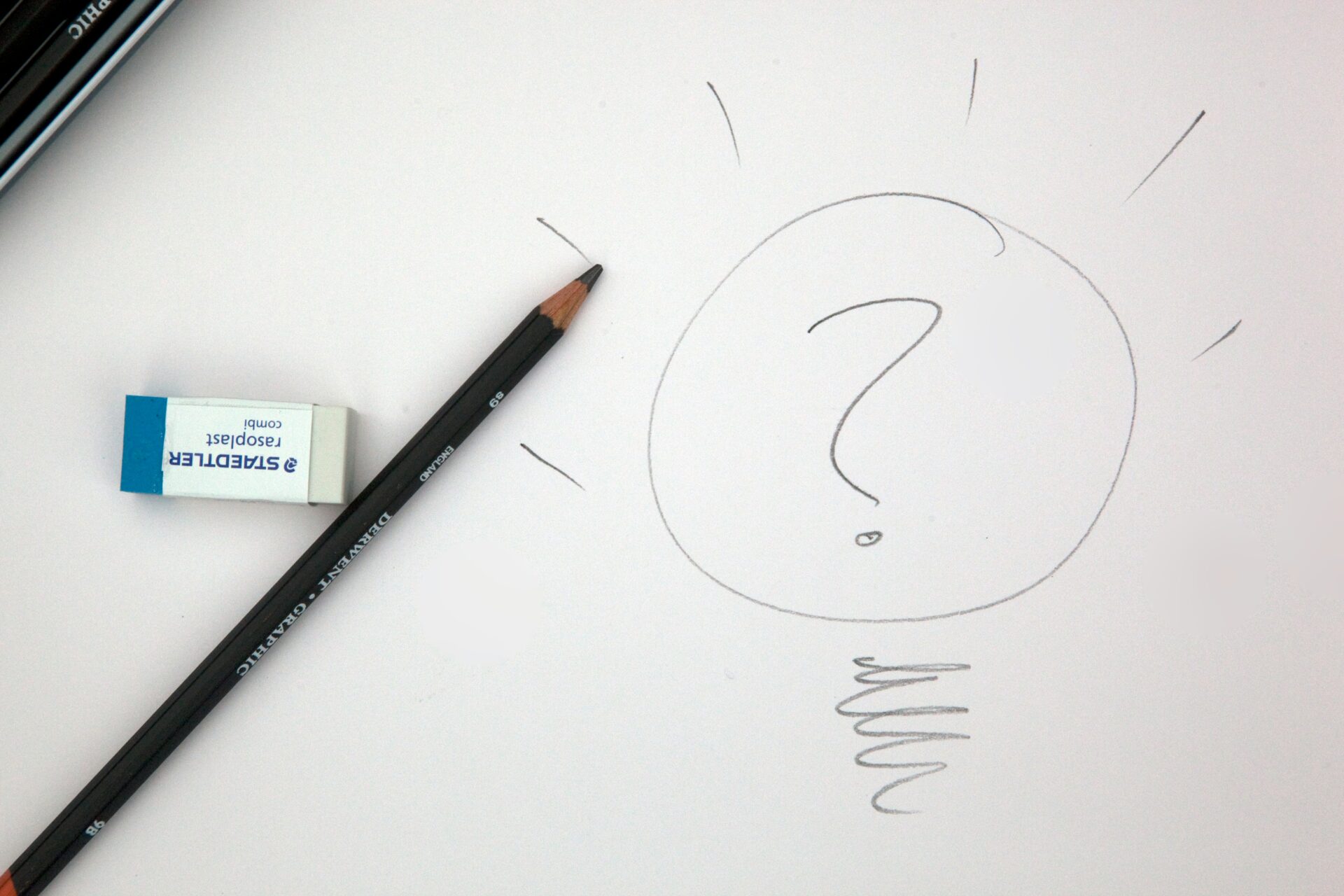
ここでお伝えしたいのは、当然ながら拙著の宣伝ではありません。
その方たちが高い質のシナリオをつくることができたのは、その方たちが元々持っていた思考力などの能力によるものが大きいと思いますし、何よりその質になるまで粘り強く考え抜き、リサーチを続けた結果です。私の本の貢献は全体の一部に過ぎません。一部というか、きっかけでしかありません。
しかし、何か新しいことを学ぶ際、最初の時点で、その分野で一般的だと考えられている体系を学ぶことは非常に重要です。
ただし、これが簡単ではないのは、私たちがすでに他のさまざまな知識を持ち、それらを使った経験を積んでいるからです。既存の知識や手法に欠点はあるものの、新しく複雑な(あるいは複雑に見える)知識や手法を学ぶことに比べれば、既存のもので良いと判断してしまいがちです。
そう判断してしまっているときは、本来の目的を忘れてしまっている可能性が高い。そのため、何かを学んでいる時、思ったように進まない不満や不安の原因を、新しく学ぼうとしているもの自体や学習方法、教材などにあるのだと言いたい衝動に駆られた際は、一度立ち止まり、もう一度目的を確認しましょう。
そして、その目的が自分の時間と労力を費やすべきものだと判断したのであれば、腰を据えて、まずは丁寧にその体系をそのままインストールすることに時間を費やしましょう。
そのような窮屈さの先には、英語であれば、シナリオプランニングであれ、それらを自分の思いどおりに使いこなせる自由が待っているはずです。
コラム執筆者:新井 宏征(あらい ひろゆき)

株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役
東京外国語大学大学院修後、SAPジャパン、情報通信総合研究所(NTTグループ)を経て、現在はシナリオプランニングやプロダクトマネジメントの考え方を応用し、事業と組織の両面からクライアントの変革を支援するコンサルティング活動に従事。
Saïd Business School Oxford Scenarios Programmeにおいて、世界におけるシナリオプランニング指導の第一人者であるRafael Ramirezや、Shell Internationalでシナリオプランニングを推進してきたKees van der HeijdenやCho-Oon Khongらにシナリオプランニングの指導を受ける。
その内容を理論的な基礎としながら、2013年の創業以来、日本の組織文化や慣習にあわせた実践的なシナリオプランニング活用支援を行っている。
資格として、PMP(Project Management Professional)、英検1級、TOEIC 990点、SAP関連資格などを保有している。
主な著書に『実践 シナリオ・プランニング』、訳書に『プロダクトマネジャーの教科書』、『成功するイノベーションは何が違うのか?』、『90日変革モデル』、『世界のエグゼクティブが学ぶ 誰もがリーダーになれる特別授業』(すべて翔泳社)などがある。
