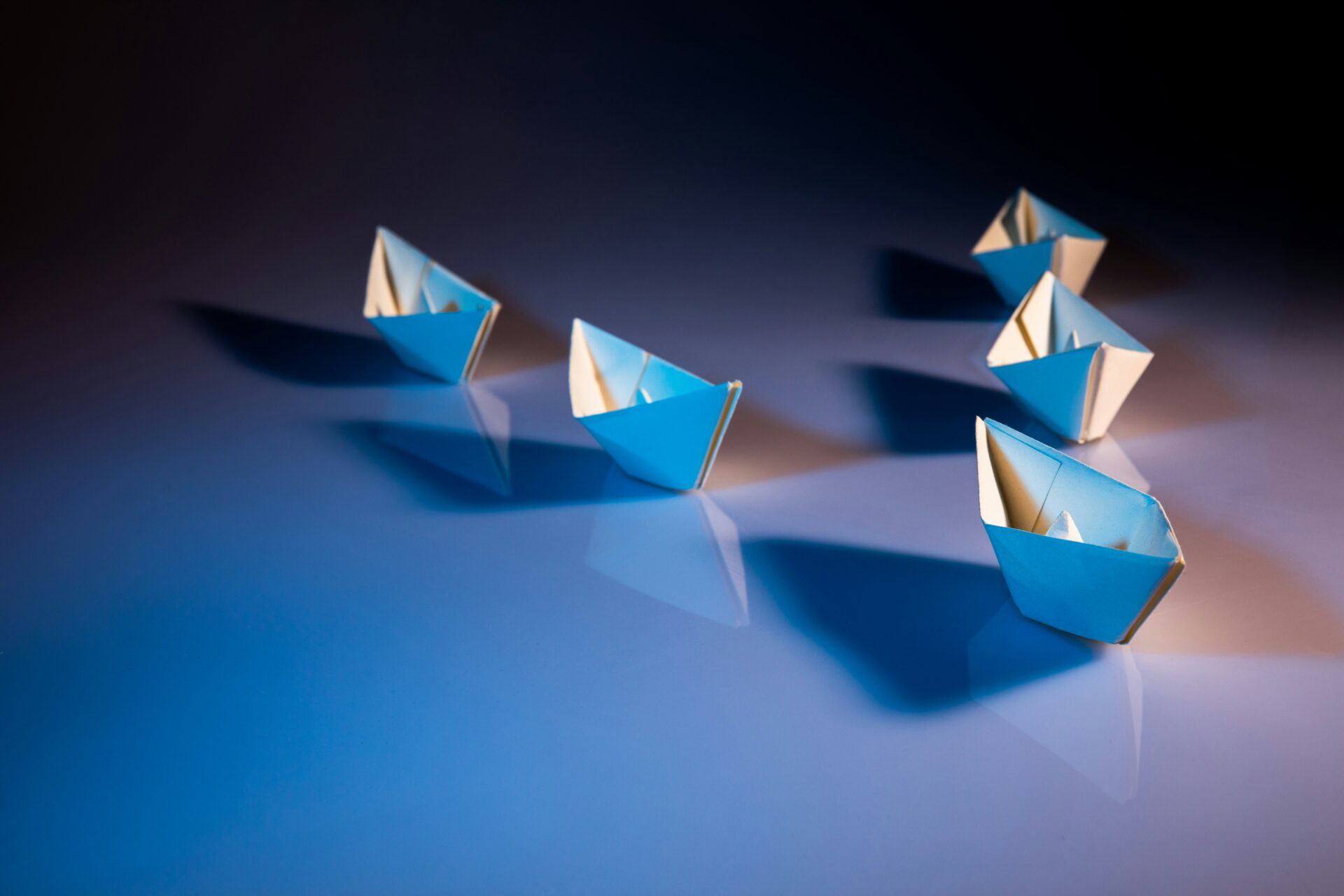目的に応じたシナリオプランニング活用設計の必要性
シナリオプランニングのさまざまな活用場面

ウェブに書くコラムとしてはだいぶ久しぶりになってしまいました。
この数ヶ月、シナリオプランニングや未来創造ダイアローグを使って、さまざまな目的でお客さまとご一緒させていただいています。
たとえば、この数週間の打合せやワークショップ、研修の機会を振り返っても、シナリオプランニングというツールを使うという点では共通していても、次のように目的はさまざまです。
- 外部環境の不確実性を考慮した経営計画等を作成したい
- 不確実性を考慮した計画を元に組織体制をどうしていくのかを検討したい
- 環境変化に伴い自社のターゲット顧客がどう変化し、どう対応するのかを検討したい
- 環境変化に伴い自社のコア技術がどう対応していけるのかを検討したい
- 環境変化に伴い自社の既存のビジネスモデルの持続可能性を検討したい
組み合わせる手法の広がり
このように目的が違えば、シナリオプランニングと合わせて使う手法も変わってきます。同じくここ数週間で活用した経営理論や手法などをザッと思い出してみると次のようなものを使いました。
- いろいろな振り返りの考え方や手法
- 共感マップ
- ビジネスモデルキャンバス
- リーンキャンバス
- ロジックモデル
- いろいろな事業戦略検討の考え方や手法
- いろいろなマーケティング戦略検討の考え方や手法
最初に書いた目的と1対1対応ではないため数が合いませんが、ここに書いたとおり、いろいろなものを使っています。
シナリオプランニングだけを学べば良いのか?

「シナリオプランニング」という手法だけを学びたいのであれば、拙著『実践 シナリオ・プランニング』やその他の「シナリオプランニングを学ぶこと」を目的とした研修などを受けるのでも十分かもしれません。
しかし、シナリオプランニングも、最初から整った手法としてあったわけではなく、元々は「このように変化し続けていく経営環境の中で、どう経営を進めていくのが良いか?」という問題意識から試行錯誤がはじまり、それが後々になって体系化されたものです。
そう考えると、単にシナリオプランニングだけを知り、実践するだけでは、その結果を企業で生かすという観点からは十分とは言えません。そもそもの目的に立ち返って、シナリオプランニングだけではなく、必要な理論や手法と組み合わせて使うことが重要です。
誰もが取り組まなければいけない時に考えるべきこと

シナリオプランニングを使って12年以上、さまざまなご支援をしてきた経験から言えば、どのような企業のどのような部署、役割であっても、外部環境と無縁で成り立っているものがない以上、何かしらの形でシナリオプランニングを活用することができます。
そして、今の時代、シナリオプランニングをとおして「不確実な変化の可能性を考える」ことは、「やっておいた方が良い」ではなく「やらなければいけない」ことに変わっています。そのことについては以前に書いたコラムにも書きました。
本当に不確実な時期のシナリオプランニング | シナリオプランニングで組織の未来をデザインする|スタイリッシュ・アイデア
ただし、誰もがやらなければいけないとなると困るのが、その実践の仕方です。「戦略や計画を立案するために使う場合」と「人材育成をするために使う場合」では、シナリオプランニング自体の使い方や他の手法などとの組み合わせ方も変わってきます。
今後、目的に合わせたシナリオプランニングや未来創造ダイアローグの使い方についても詳しくご紹介していこうと思っていますが、まずはぜひ、「自分たちが取り組む目的を元にすると、シナリオプランニング以外にどんな手法や考え方を使えば良いのか?」と考えるところから始めるようにしてください。
コラム執筆者:新井 宏征(あらい ひろゆき)

株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役
東京外国語大学大学院修後、SAPジャパン、情報通信総合研究所(NTTグループ)を経て、現在はシナリオプランニングやプロダクトマネジメントの考え方を応用し、事業と組織の両面からクライアントの変革を支援するコンサルティング活動に従事。
Saïd Business School Oxford Scenarios Programmeにおいて、世界におけるシナリオプランニング指導の第一人者であるRafael Ramirezや、Shell Internationalでシナリオプランニングを推進してきたKees van der HeijdenやCho-Oon Khongらにシナリオプランニングの指導を受ける。
その内容を理論的な基礎としながら、2013年の創業以来、日本の組織文化や慣習にあわせた実践的なシナリオプランニング活用支援を行っている。
資格として、PMP(Project Management Professional)、英検1級、TOEIC 990点、SAP関連資格などを保有している。
主な著書に『実践 シナリオ・プランニング』、訳書に『プロダクトマネジャーの教科書』、『成功するイノベーションは何が違うのか?』、『90日変革モデル』、『世界のエグゼクティブが学ぶ 誰もがリーダーになれる特別授業』(すべて翔泳社)などがある。